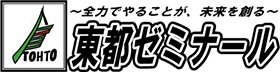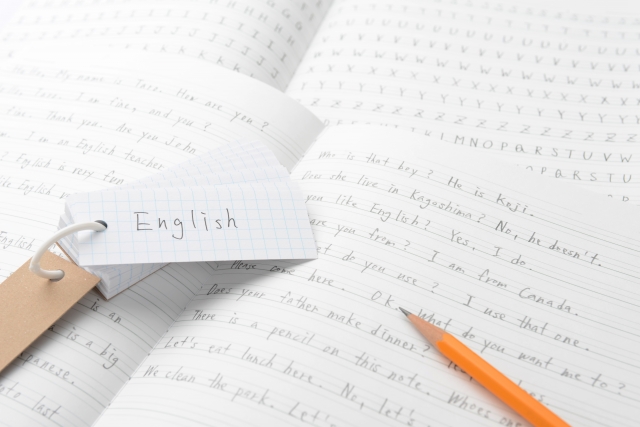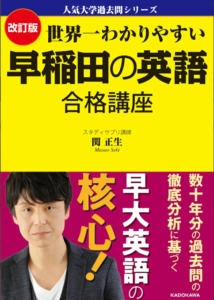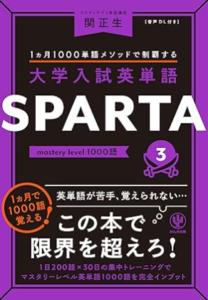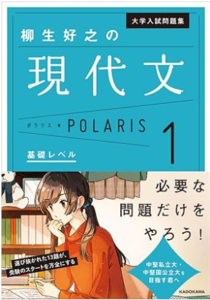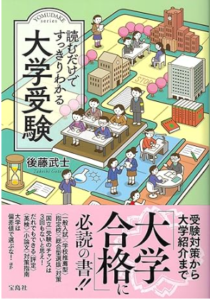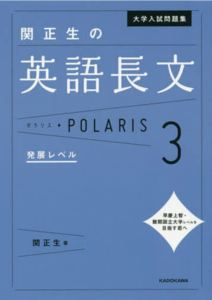暗記がスラスラできない。
なかなか覚えられない。
もの覚えが悪いのではないか。
定期テスト前はもちろん、ちょっとした小テストでも、普段からもそう感じる人、多いのではないでしょうか。
暗記というといい印象がないというのが、おおかただと思います。
でも、暗記できていないと先へ進めない、何も解けない。
これもまた事実です。
ここでは5科目、定期テストの対策を前提に、
読めばすぐわかる、今すぐ実践できる、
暗記のしかたのポイント5つをまとめました。
ずばり!大事なポイント5つ

五感を使う
五感というと嗅覚や味覚などもさしますが、
使えるものはすべて使ってというふうにとってくれるといいです。
ここでは特に「見る」「書く」「声を出す」ことだと思って下さい。
よく英単語は書いて覚えろ、声を出して覚えろ、と言われます。
漢字も書いて覚えなさいと。
しかしなにもそれらに限ったことではないです。
語句や理科、社会も、すべてに通じます。
漢字ばかりではなく、慣用句や故事成語、決まった表現も書く。
理科社会の知識事項も書く。一問一答の答えも書く。
こういうことです。
見ているだけで覚えられたら苦労しません。
何でもすぐ暗記できて、困ることも悩むこともないはずです。
でも実際は違いますよね。
難しいことをするわけではないです。
書くとともに声も出して、言いながら進めていけばいいのです。
今まで習慣がなかったりして初め抵抗を感じるようであれば、まず声を出すだけでも違います。
「見る」とともに声を出しているわけですから、これだけでも2倍分のことをやっているわけです。
これに「書く」ことをしていけばよいのです。今までと同じ時間で3倍分の勉強ができます。
いや、手を動かして、見て言って、耳で聞いてというふうに考えれば、それ以上のことをしていることにもなります。これなら確実に暗記が身につきます。
PS:身近な例『不規則動詞の暗記』
始めはバラバラに感じても、書いて声に出すことで、
似た発音の語はつづりも似ていることがはっきりわかるはず。
変化にいくつかの似ているパターンがあることにも気付くでしょう。
以後はスラスラ出来るようになります。
これは他の全ての単語にも当てはまりますね。
語呂合わせ
定番ですね。
★昔からある有名なもの
★誰かが作ったものを拝借
★自分オリジナルでつくる
どんな形でも構わない。覚えられればいい。
そして、年号や、公式、出来事や人物などに限らず、数字にしても言葉でも、また、科目を超えて何にでも使えます。
自分オリジナルで作る場合は、ストーリー性を持たせたり、五・七・五・・・と詩歌のようにしたり、頭文字をつなげたりと工夫する。
半ば強引!でも構いません。
こうすることで、かえってはかどったり、楽しくなったりもして暗記が進むことにつながります。
語呂合わせは“定番”“王道”です!
PS:身近な例『趣味に合わせる』
私事ですが、自分は鉄道やバスが好きです。数字に関しては、これを利用しました。
形式や用途などによって区分されている数字、特徴ある特定の番号、マニアックな数字など、これがけっこう使えたのです。
反復
いろいろ工夫しても、やはりこれがないことにはどうにもなりません。
暗記でも必要です。あとはやり方。
1日何回か分けてその度にひたすら書く
数時間後、翌日、2~3日空けて、覚えているかチェックする
手が空いたり時間が空いた時に確かめる
など、人によって工夫努力していることが多いようです。
効率よく、身に付く方法は、
★10個なら10個をその日に覚える
★次の日にその10個+新たな10個
というものです。
こうして、日々増やしていけば難なく覚えていけます。
あとは前述のやり方を組み合わせれば上手く進むはずです。
参考までに、
英語は、単語・熟語・本文暗記→問題集
理数は、解き方や理解を重視
これでテスト対策していくとなかなかうまくいきます。
PS:身近な例『うちの塾生』
単語や漢字・語句の暗記を毎日増やしていく方法で確認テストをしていますが、地道にやっているほど確実に身について、忘れません。成績UPも早いし伸びます。手を抜いたりサボっていると暗記に時間がかかったり、再テストになります。
ノートの活用
ここでは“まとめ”というより、とにかく“書く”というノートです。
声に出して書く、というそれをするためのノートと思って下さい。
また、何も言葉や答えを書くだけでなく、覚えているかどうかを図に書いて示すことに使うノートです。
モノによっては図示できることで覚えているか確かめることになります。
こういう使い方になるので、安物や余り物のノートがいいです。
五感を使って暗記ですから、必ず用意して書きましょう。
PS:身近な例『余ったノート』
ノートの使い方をテーマにした回で、ノートの欠点の一つに、場合によっては“余る”ということを挙げました。
そんな風になっているノートで、もうどんどん使ってもいい場合に使えば無駄もないですよね。
自分はよくそういう使い方をしました。
体の管理
これもよく言われることです。
いくら頑張っても、頑張ろうとしても、体調が悪くてはどうにもなりません。かえって何もできないとか、効果がなく、無駄になってしまいます。
スポーツ、日々の生活と同じく、
暗記にも暗記に必要な“体”“脳”がいるのです。
万全な態勢にしてこそ、どんなこともしっかりと出来ます。
まあそこまで固く考えずに、普段からごく普通に体調管理をしていれば問題はありません。
要は「睡眠」「食事」「適度な運動」です。
睡眠は、寝ている間に知識が整理されて起きた時にはすっきりした状態になっている、などとよく言われます。
適度な運動は、気分転換にもなり効率よい勉強につながると聞きますよね。
一夜漬けは実のところどうなのか
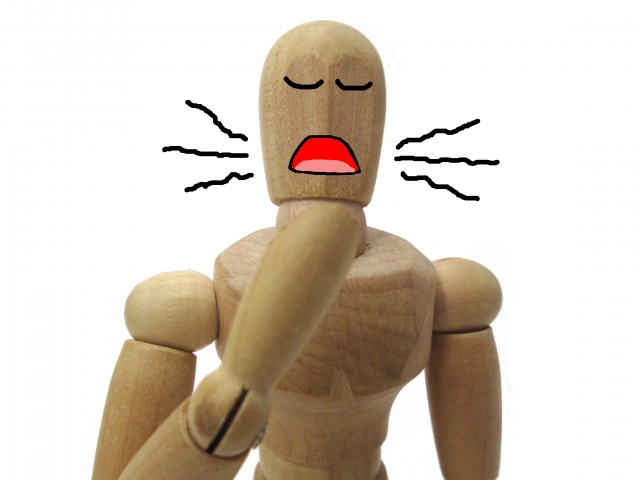
そこで「睡眠」が関わってくる、いわゆる“一夜漬け”はどうなのだろうか? ということが気になります。
割と否定的なイメージを感じますが、
意外に、賛否両論あるようです。
周りに聞いてみても分かれますね。
睡眠時間が減るとか、そもそも“寝ない”からよくないというのが否定的な考えで、体調面から見ればそのとおりです。暗記できていたものもきちんとアウトプットできなくなる恐れもあります。
では、一夜漬けもよしとする意見とは?
国語だったら漢字・語句、音読、
英語だったら単語・熟語
数学だったら基礎的な計算
このへんです。
暗記するというよりは、確認に近い面があります。
できる範囲内のものをできる分だけとも言えるでしょう。
人によってやれる能力的な面もあると思いますが、
その人にとってできることをやればよいということになるかと思います。
周りに合わせる必要なし、無理もしてはいけない。
もっとも、一夜漬けしなくてはならない状況を作らないことが一番です。
90点以上を取りに行く場合
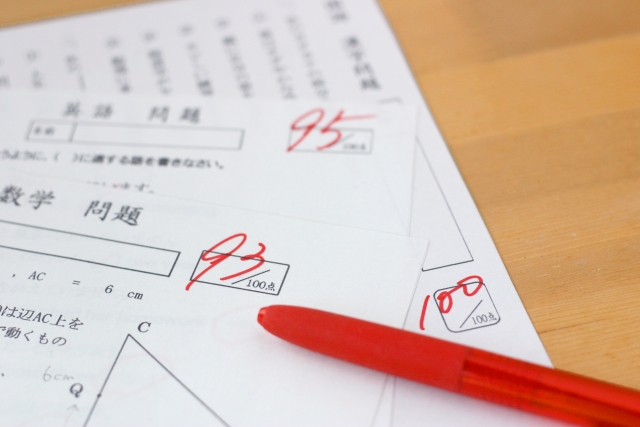
最上位狙いの場合です。
こうなると暗記だけでは足りません。
応用までをこなしておいてテストに対応しないといけないからです。
100点取らせない問題を出題してくることもしばしばあります。
対策として、
★学校ワークは応用発展問題まで解く
★市販の問題集ならそれも発展レベルまでこなす
★塾のテキストも発展レベルまでやっておく
これを暗記や通常の演習のあと、最後にこなしておくのがポイントです。
上位狙い、やれる力がある人は挑戦して下さい。
まとめ
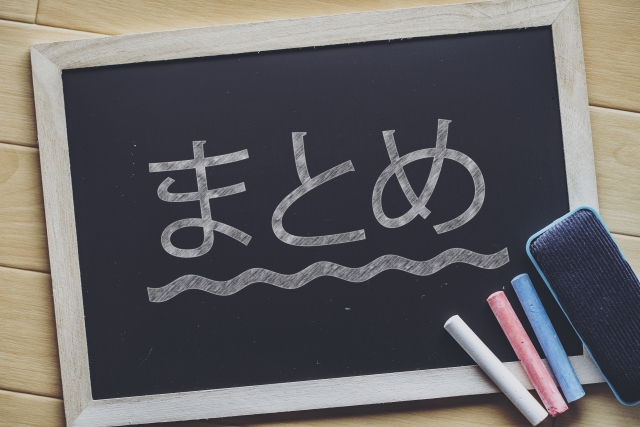
いかがでしたか。
暗記に役立つ5つのポイントです。
①「見る」「書く」「声を出す」こと
どれかひとつ欠けてもいけない。
1回の取組みで3つのことをすることになるので、
同時にやってこそ効果が出ます。
②語呂合わせでいく
有名なもの、昔から使われているもの、もちろんよし。
自分オリジナルでつくったものもOK。
これだとなかなか頭に入るというもの。
③反復する
やはりこれがないと意味がありません。
暗唱とともに工夫もする。
時間を置いて繰り返すとか、スピードアップしていく。
④ノートの活用
ひたすら書くノートでよい、無いよりはずっといい。
「書く」ことにもつながる。
整って書いていけるので暗記もはかどるというもの。
⑤体調管理を忘れないこと
体調が良いからこそ暗記も進む。
悪いと暗記したことがアウトプットできなくなる。
暗記にも「睡眠」「食事」「適度な運動」
このようにやっていなかった、足りないところがあった、
などあれば改善しましょう。
続けることも大切です。単純作業なだけに、地道な努力が必要。
でもこれで、定期テストも基礎知識もバッチリです。